六書や漢字の成り立ちについての知っていることすべてをこの記事でまとめて載せました。情報をわかりやすくするために学習ノートみたいな感じで公開します。徐々に記事にある情報を満たせる予定なので、今の状態だと情報量が少ないことがあるかもしれません。皆さんの学習の役に立てたらなと思います。参考にしたサイトを記事の最後に残しました。
ノートの内容
六書
六書→漢字の成り立ちの分類。
造時法(成り立ち)と用字法(用法)に分ける。
●造字法の六書
象形、指事、会意、形声
●用字法の六書
転注、仮借
象形は成り立ちの方法のことで象形文字は象形で作られた字のこと。
成り立ちに関する研究がまだ進んでいて、常に新しい発表が出ている。
したがって誤ってる説がいまだに多い。
特に文字が誤って会意とされてる古い説が多い(例:信、庭、昔、、、)
造字法
字をクリックでウィクショナリーに移動。
●象形(しょうけい)
物の形を象って(真似して)文字を作る方法。象形文字の例:木、火、川、山
●指事(しじ)
形で表しにくいものを点や線の組み合わせで文字を作る方法。指事文字の例:上、下、中、本
●会意(かいい)
すでに存在する文字を二つ以上合わせて別の意味する文字を作る方法。会意文字の例:明、休、林、好
●形声(けいせい)
意味を表す字と音を表す字を組み合わせて新しい文字を作る方法。形声文字の例:情、暗、緑、銅
もっとも数の多い造字法のは形声。もっとも少ないのは象形。
用字法
●転注(てんちゅう)
漢字の本来の意味から他の意味に転用して新しい意味を作る方法。転注文字の例:昔音楽を表した「楽」に音楽がたのしいの理由して「楽しい」を意味するようになった。
→転注の一つの説。決定な定義が存在しない。
●仮借(かしゃく・かしゃ)
ある意味を表す文字に発音が似てた別の意味を入れる方法。仮借の例:元々「切」の漢語を表した「七」が仮借して、昔古代中国で発音がにてた「なな」を意味するようになった。他に仮借文字の例:我、豆、七、其
更新の速さ、研究にかかわる情報の根源などでウィクショナリーが現在もっとも信頼度高い漢字成り立ちの資料となってます。
国字
漢字がほとんど古代中国で成り立ったが古代日本で成り立った字もある。日本由来の字は国字という。
国字の例:働(日本で成り立った漢字である動の異体字)、込(会意文字で、すすむを意味する辵といれるを意味する入の組み合わせ)、畑、峠、畑など
ノートに使った資料
1.ウィクショナリー
2.漢字辞典オンライン

3.学研キッズネット


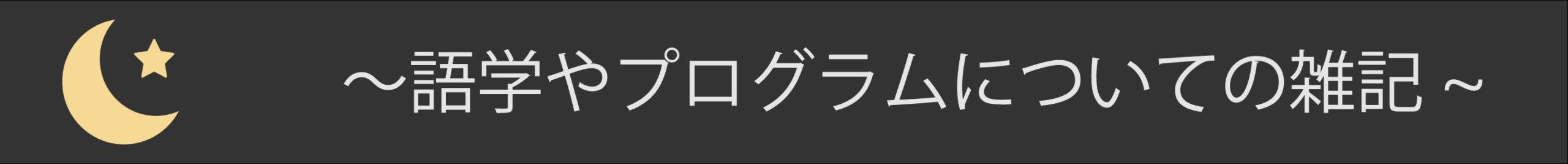
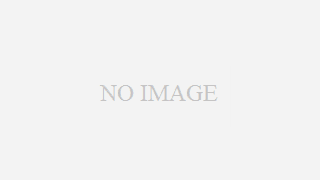

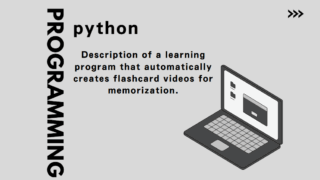
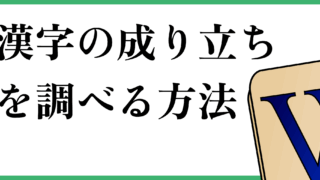
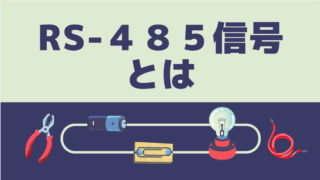
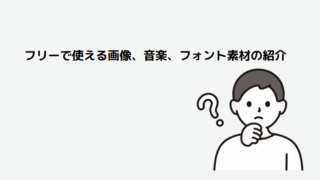
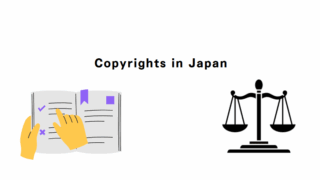
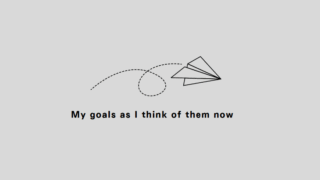


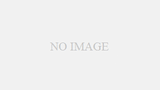
コメント