この記事では自分の六書の学習メモを公開します。
六書とは
六書とは、古代中国の「説文解字」に規定された漢字の作り法則。

象形、指事、会意、形声、転注、仮借の六つが六書という。
六書の構成
最初の三つが造字法。後の三つが運用法。 また、象形と指事は物の形状を、会意と形声は組織の組み合わせ、転注と仮借は文字そのものの応用であるとする、各々三つにペア分類できることを「六書三耦説」という。
>>やたがらすナビ
象形
象形(しょうけい)は、物の形を象って(真似して)字形を作ること。象形は造字法の中から文字の数は最も少ない法則で、文字の1割以下が象形文字となっています。
象形文字の例には、
1.木一本を象る「木」
2.燃える火を象る「火」
3.流れる水を象る「川」
4.山の形を象る「山」
と他にも力・止・船・刀・虎などが該当します。
指事
指事(しじ)は、形で表しにくいものを字形の組み合わせで表すこと。
指事文字の例には、
1.上部をあらわす「上」(異体字:丄)
2.下部をあらわす「下」(異体字:丅)
3.中心をあらわす「中」
4.もとをあらわす「本」
などが該当します。
会意
会意(かいい)は、象形と指事によって作られた文字を組み合わせて新しい意味をを作ること。
会意文字の例には、
1.象形文字の「日」と「月」を組み合わせた「明」
2.象形文字の「人」と「木」をを組み合わせた「休」
3.象形文字の「木」二つを組み合わせた「林」
4.象形文字の「女」と「子」を組み合わせた「好」
などが該当します。
形声
形声(けいせい)は、意味を表す字と音を表す字を組み合わせて新しい字を作ること。意味を表す字は意符(いふ)といい、音を表す字は音符(おんぷ)という。象形と反対に、形声で作られた文字は六書の大半をしています。
●音符は声符(せいふ)ともいいます。
形声文字の例には、
1.意符の「心」と音符の「青」を組み合わせた「情」
2.意符の「日」と音符の「音」を組み合わせた「暗」
3.意符の「糸」と音符の「彔」を組み合わせた「緑」
4.意符の「金」と音符の「同」を組み合わせた「銅」
などが該当します。
さらに「情」に関しては、字の音符の「青」自体も形声であり、情と違って意符+音符の組み立てからではなく音符+音符の形で作られ、同じ音の「生 *TSEŊ/」と「井 *TSEŊ/」から作られた字である。
音符と音符を組み合わせた形声文字は両声字(りょうせいじ)といい、他に両声字に該当する文字は静、盟などがあります。
転注(轉注)
転注(てんちゅう)は、漢字の本来の意味から他の意味に転用して新しい意味を作ること、という一説がありますが、決定な説が存在しないため可能な説の一つと考えています。
転注の例には、
1.音楽・楽器を表した「楽(ガク)」が、音楽がたのしいと考えれるので「楽しい、楽(ラク)」を意味するようになりました。
などがあります。
仮借
仮借(かしゃく・かしゃ)は、他の同音・類似音の字を借用すること。
仮借の例には、
1.「切」表した「七」が仮借して、発音がにてた理由で「なな」の意味で用いる。
2.「のこぎり」を表した「我」が仮借して、発音がにてた「われ」の意味で用いる。
3.「たかつき」を表した「豆」が仮借して、発音がにてた「まめ」の意味で用いる。
4.「ちりとり」を表した「其」が仮借して、発音がにてた「その」の意味で用いる。
などが該当します。
まとめ
六書とは漢字を作る法則で、象形、指事、会意、形声、転注、仮借の六つにわけてます。
六書を分類する方法は「六書三耦説」といい、最初の3つを造字法で、後の三つが運用法に分け、象形と指事は物の形状、会意と形声は組織の組み合わせ、転注と仮借は文字そのものの応用の三つペアにわけます。

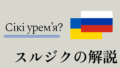

コメント