こんにちは。この記事では漢字の成り立ちの分類、六書についてお伝えしたいと思います。六書は漢字の成り立ち(造字法)と用法(用字法)に分類され、まとめて6つの方法を含めます。
造字法
造字法は象形(しょうけい)、指事(しじ)、会意(かいい)と形声(けいせい)の4つ存在します。
象形
物の形を真似して文字を作る方法。つまり見た目のままに字を作ります。例えばきの形を表す「木」とかはわかりやすいだと思います。
指事
形で表しにくいものを点や線の組み合わせて文字を作る方法。
会意
すでに存在する文字を二つ以上合わせて別の意味する文字を作る方法。
形声
意味を表す字と音を表す字を組み合わせて新しい文字を作る方法。例えば「緑」が意味を表す糸と音を表す彔の組み合わせとなります。
用字法
用字法は転注(てんちゅう)と仮借(かしゃく・かしゃ)の2つに分類されます。
転注
漢字の本来の意味から他の意味に転用して新しい意味を作る方法。例えば昔音楽を表した「楽」に音楽がたのしいから「楽しい」って意味するようになりました。
*ウィキペディアにより転注に決定の説が現在には存在しないため、この説が絶対正しいとは限らない。
仮借
ある意味を表す文字に発音が似てた別の意味を入れる方法。例えば元々「切/tsʰˤik/」の漢語を表した七が仮借して発音がにてた「なな/tsʰik/」を意味するようになりました。
まとめ
漢字の成り立ちの分類、六書を説明しました。例に使った文字の成り立ちはウィクショナリーから調べることができ、ウィクショナリーの使用について前に書いたこちらの記事をご確認いただくさい。

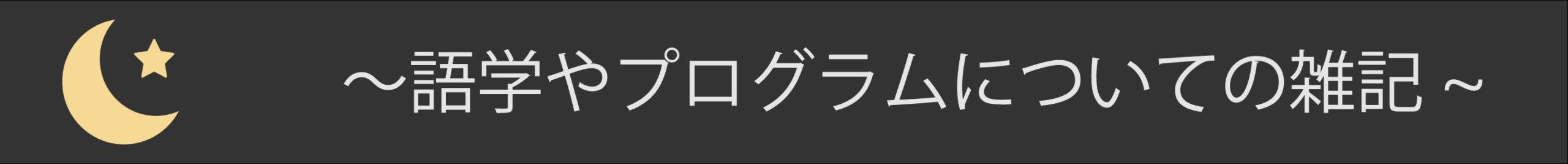

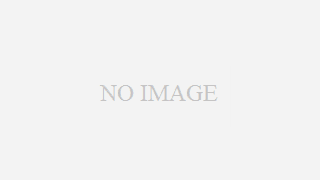
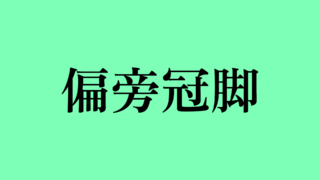


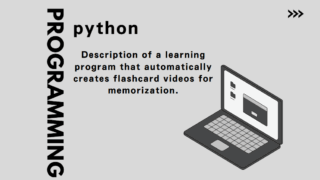
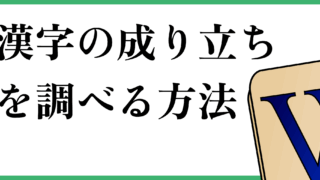
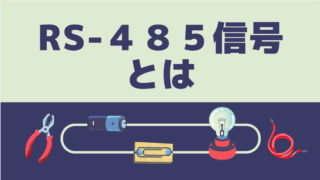
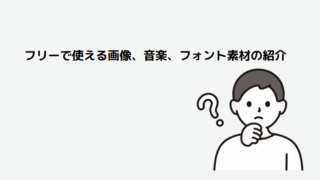
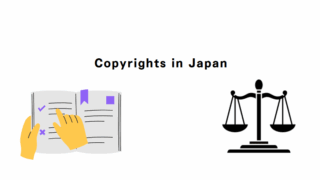
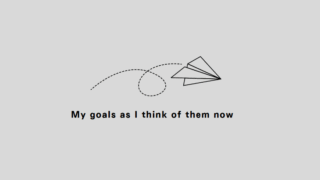


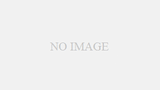
コメント